
ブログ
住まいの豆知識から
暮らしのヒントなどご紹介
このブログ記事もおすすめ!
【放置厳禁】擁壁のひび割れ・傾きは大事故に!所有者に責任も?

こんにちは🌞広報の中村です~!
今回は、決して他人事ではない、私たちの安全と財産に関わる非常に重要なお話です!
先日、擁壁(ようへき)の不具合が原因で住宅が倒壊したという怖い事故が報じられました。幸い、お住まいの方は無事だったとのことですが、もし自分の隣の家や、自分自身が所有する土地の擁壁で同じことが起きたらどうなるでしょうか…?😭
この記事では、擁壁の役割から、ひび割れや傾きが発生する具体的な原因、そして所有者の管理責任など、詳しく解説します。悲劇を未然に防ぐために、ぜひ最後まで読んで今日からできる対策を始めてください💪
目次
実は深刻!「施工の不備・欠陥」と「地盤の弱さ」による構造的な問題
なぜ擁壁(ようへき)は必要?役割と種類を正しく理解する

擁壁のトラブルを聞くたびに、「自分の家の擁壁は大丈夫だろうか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。しかし、そもそも擁壁がなぜそこに存在するのか、その本質的な役割を理解していなければ、適切な管理や点検はできません。
ここでは、擁壁の定義や、高低差のある土地を守る「命の壁」としての重要性、そしてその構造的な違いを解説します。擁壁の正しい知識を持つことが、事故を未然に防ぐための第一歩です。
擁壁とは?土砂崩壊を防ぐ「命の壁」の定義と機能
擁壁とは、高低差のある土地において、土砂の崩壊(土垂れや土砂崩れ)を防ぎ、地盤の安定を保つために設けられた壁状の構造物です。単なる仕切りではなく、家や周辺住民の安全を守る「命の壁」として非常に重要な役割を担っています。🛡️
斜面を切り取ったり土を盛り上げたりした土地は、重力や雨水の影響で常に崩れようとする「土圧(どあつ)」を受けています。擁壁は、この土圧をしっかりと受け止め、背後の地盤を安定させるために、専門的な構造計算のもとに設計・施工されています。
擁壁が持つ主な機能は、以下の2点です。
・土圧の保持:背後の土砂が持つ水平方向への力を受け止め、地盤が崩れるのを防ぎます。
・宅地の有効活用:傾斜地を平坦な段差(ひな壇)に変えることで、住宅や駐車場として土地を有効に利用できるようにします。
特に土のうを積んだだけの簡易的な土留めや、現行の建築基準を満たさない古い石積みなどは、土圧に耐えられず大事故につながるリスクがあるため、擁壁の定義や構造を正しく理解することが大切です。
擁壁の存在意義は、人々の生活と安全を土砂崩壊のリスクから守ることにあります。見た目の壁の裏側で、常に大きな土圧を受け止めている構造物であることを理解し、適切な管理意識を持つことが重要です。
高低差のある土地で擁壁が果たす「3つの重要性」
擁壁は、土を支える構造的な機能に加え、「建築の許可」「土地の資産価値」「所有者の安心」を担保する、不動産としての極めて重要な役割を果たしています。この擁壁の法的・経済的な側面を理解することが、適切な維持管理の意識につながります。
適切な擁壁がない高低差のある土地は、建築基準法や宅地造成等規制法の観点から、安全な宅地として認められません。そのため、擁壁は単なる構造物ではなく、土地に建物を建てるための法的な条件を満たし、資産価値を確定させるための必須要件なんです
擁壁が私たちの暮らしにもたらす具体的な重要な点は以下の3点です。
・建築の許可条件:建築基準法に適合した擁壁がなければ、原則としてその土地に建物を建てることができません。擁壁は、安全性を証明するために必要です。
・土地の資産価値の維持:擁壁が適切に整備されていることで、売買する際にも安全性が担保され、土地の価格や評価が安定します。老朽化した不適格擁壁は、かえって資産価値を下げる原因となります。
・災害リスクの軽減と安心:地盤の崩壊リスクを軽減することで、住民の物理的な安全だけでなく、いつ崩れるかわからないという精神的な不安も解消し、安心感のある暮らしを提供します。
擁壁は、単に土を留めるだけでなく、土地の価値と利用可能性を左右する重要な要素です。この法的・経済的な重要性を理解し、適切な状態を維持していくことが、所有者としての最大の責務となります。
知っておきたい!安全性が異なる擁壁の主な種類と特徴
擁壁の安全性や耐久性は、その構造と材料によって大きく異なります。特に、現行の建築基準を満たす擁壁と、そうではない擁壁を見分ける知識は大切になってきます。
擁壁は、土圧に耐えるために様々な手法でつくられています。これらの設計が適切でないと、地震や豪雨などで土圧に耐えきれず、構造的な欠陥から倒壊リスクが高まってしまいます。
擁壁は大きく分けて、「自重式」と現在の建築基準法に適合しない「不適格擁壁」に分類されます。
・L型擁壁(自重式):鉄筋コンクリート造で、横から見るとアルファベットのLの形をしています。擁壁の下側に底盤が宅地側に張り出すことで、底盤上の土の重さを利用して土圧に抵抗します。
・逆T型擁壁(自重式):鉄筋コンクリート造で、横から見るとアルファベットの逆になったTの形をしています。擁壁の両側に底盤が張り出すため、L型よりも安定性が高く、大きな土圧に抵抗できます。
・重力式擁壁(自重式):コンクリートや石材の自重のみで土圧に対抗する擁壁。構造的な安定性は高いですが、現行法では、高さや使用できる材料に厳しい制限があります。
・空石積みや練石積みなど(不適格擁壁⚠️):古いものなど、現行の基準を満たしていない擁壁をまとめて言います。構造計算されていないため、亀裂や傾きが発生した場合、極めて危険です。
L型と逆T型は、どちらも高い安全性を持つ適合擁壁ですが、敷地の条件に応じて適切な形式を選ぶ必要があります。一方で、古い擁壁は特に注意が必要です。擁壁の種類と安全性を把握し、不適格擁壁の場合は早期に専門家に相談しましょう。
これまで、擁壁が単なる構造物ではなく、土砂崩壊を防ぎ土地の価値を担保する「命の壁」であることを解説しました。特に、擁壁はL型・逆T型といった適合擁壁だけでなく、強度が不足しがちな不適格擁壁も存在します。ご自宅や所有地の擁壁がどのような種類で、どのようなリスクを抱えているのかを知ることが、正しい管理につながる第一歩です。
擁壁の不具合が「大事故」につながるメカニズムと所有者の責任

少しのひび割れなら大丈夫だろうと見過ごしていませんか? これが取り返しのつかない大事故につながる可能性は否定できません。擁壁の小さな不具合は、豪雨や地震をきっかけに、土砂崩壊や家屋倒壊という最悪の事態へと急激に発展する場合があります。さらに深刻なのは、管理不十分による事故が発生した場合、擁壁の所有者として「工作物責任(賠償責任)」を負う可能性があることです。
ここでは、不具合がどのように大事故へ発展するのかというメカニズムと、所有者に課せられる重大な法的責任について詳しく解説します。自分の責任範囲を知り、早急な対策を講じるための危機意識を持ちましょう。
小さな不具合が致命傷に!擁壁崩壊までのメカニズム
擁壁の小さなひび割れや水抜き穴の詰まりは、水の侵入と滞留によって深刻化し、最終的に擁壁を外側に押し出す力が限界を超えて崩壊に至るという進行メカニズムを持っています。見過ごしがちな初期症状は致命傷に直結するサインです。
擁壁の背後にある土は、水を含むと比重が増し、擁壁を押し出す土圧が急激に増大するからです。構造計算で想定された強度を上回る水圧がかかり、ひび割れが拡大したり、擁壁が外側へ傾いたりする現象を引き起こします。
擁壁崩壊に至る一般的な進行メカニズムは以下の通りです。
・水抜き穴の詰まり:枯れ葉や泥などで水抜き穴が詰まると、擁壁背面に水が溜まり、土の飽和状態(水分を最大限に含んだ状態)が進みます。
・土圧・水圧の増大:豪雨などで水が抜けない状態が続くと、土圧に加え水そのものの重さによる水圧が擁壁にのしかかり、構造物を外側に押し出します。(はらみとも言われます)
・鉄筋の腐食:コンクリートのひび割れから水が侵入すると、内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートを内側から割ります。これにより擁壁の強度は急激に低下します。
・傾き・倒壊:上記の要因が進行した結果、地震やさらなる豪雨といった外からの力が加わった際に、擁壁の安定性が失われ、一気に崩壊に至ります。
擁壁の崩壊メカニズムは、水が鍵を握っています。排水不良やわずかなひび割れといった不具合の小さなサインを放置せず、水が適切に抜けているかを日常的にチェックすることが、大規模な事故を防ぐ上で重要です。
他人ごとではない所有者が負う工作物責任と賠償リスク
擁壁の管理が不十分なことが原因で事故が発生した場合、擁壁の所有者は被害者への損害賠償責任を負うことになります。これは、所有者に落ち度がなかったとしても責任を免れない無過失責任であり、所有者にとっての法的リスクとなります。⚖️
日本の民法では、土地の工作物(擁壁や建物など)に欠陥があり、それによって他人に損害を与えた場合、その工作物の所有者が最終的な責任を負うと定められているからです。擁壁は自然物ではなく、人がつくった工作物にあたります。
工作物責任により以下のような事態になる可能性があります。
・対第三者への賠償:劣化した擁壁が崩壊し、通行中の人に怪我を負わせてしまった場合や、隣家の建物や車を破損させてしまった場合。
・責任:この責任は、日頃から注意を払っていたという占有者(土地を借りている人など)の注意義務とは異なり、所有者は構造的な欠陥があったという事実だけで責任を負います。賠償額は、人命に関わる場合は非常に高額になる可能性があります。
・被害者にも加害者にもなるリスク:擁壁トラブルの際、自分や家族が被害者になるだけでなく、近隣の第三者に対して加害者という立場になり、法的な責任を問われるリスクがあるのです。
擁壁の適切な管理は、自分の安全を守るためだけでなく、所有者として法的・経済的な責任から逃れるための最低限の義務です。擁壁を放置することは、常にリスクを抱えることを意味すると認識しておくことが大事です。
擁壁の不具合は、単なる劣化ではなく水がカギを握った明確な進行メカニズムによって大事故へと発展すること、そして事故発生時には所有者が高額な賠償責任を負うリスクがあることを説明しました。擁壁の維持管理は、自分や家族の安全を守る行為であると同時に、法的な責任を果たすための義務なのです。
【要注意】擁壁に不具合が発生する主な原因と仕組み

擁壁のトラブルは、単に古いから起こるというわけではありません。水や地盤、施工不良など、複合的な要因が長い年月をかけて擁壁の強度を奪っていきます。特に、所有者が見落としがちな排水の不良や、目に見えない施工時の欠陥が致命傷となることも少なくありません。ここでは不具合の主な原因を4つにわけて解説します。
擁壁トラブルの最大の敵!「排水の不良」と過剰な水圧の仕組み
擁壁トラブルの最も重要かつ深刻な原因は、擁壁の背後で水が適切に処理されない排水の不良です。排水不良は過剰な水圧を生み出し、擁壁を外側に押し出す力が限界を超える最大の要因となります。
擁壁は土圧に耐えるよう設計されていますが、背後の土が大量の雨水などで飽和状態になると、土の比重が増すだけでなく、水そのものの重さや浸透圧による強力な水圧が構造物に直接かかるからです。この複合的な力が、設計強度を大きく上回って擁壁を破壊へ追い込むのです。
排水不良を引き起こす具体的な仕組みは以下の通りです。
・水抜き穴の詰まり:擁壁の前面に設けられた水抜き穴が枯れ葉や泥、雑草の根などで詰まると、背面に溜まった雨水が抜けず、擁壁内部の水の水位が上昇します。
・裏込め材の目詰まり:擁壁と土の間に敷設された砕石(裏込め材)が、細かい土粒子によって目詰まりを起こすと、水がスムーズに流れなくなります。
・水圧の増大と変形:水が溜まり続けると、擁壁全体に均等でない水圧がかかり、ひび割れ、はらみ、傾きといった目に見える変形を引き起こします。一気に崩壊のリスクが高まります。
擁壁の安全は、水が抜けることにかかっています。擁壁の異常を見つけるだけでなく、水抜き穴が機能しているかを定期的にチェックし、水が溜まらない環境を維持することが最も効果的な対策です。
避けられない問題!「経年劣化」と「自然災害」によるリスク
擁壁は、いくら構造が頑丈であっても、老朽化や地震と豪雨といった自然災害による損傷は避けることができません。これらは不可抗力とも言えますが、日頃の備えを怠れば一気にリスクを高めるため、特に注意が必要です。
擁壁の主要材料であるコンクリートには耐用年数があり、時間の経過とともに中性化や表面の剥離が進みます。また、地震の揺れは擁壁に設計以上の大きな揺れや地盤の変動をもたらし、豪雨は短時間で許容範囲を超えた水圧をかけるため、耐久性が一気に低下します。
経年劣化と自然災害が引き起こす具体的な損傷は以下の通りです。
・経年劣化(材料の劣化)
中性化と爆裂→コンクリートが空気中の二酸化炭素を取り込み中性化すると、内部の鉄筋が錆び始めます。鉄筋が錆びて膨張すると、外側のコンクリートを押し割り、大きなひび割れや剥離(爆裂)を引き起こし、強度を低下させます。
耐用年数の超過→擁壁の種類にもよりますが、設計耐用年数を超えると、構造全体の老朽化が進み、特に古い石積み擁壁などは非常に危険な状態となります。
・自然災害の影響
地震→地震動による揺れそのものだけでなく、液状化などの地盤変形によって擁壁の基礎部分が沈下(不同沈下)したり、構造的な亀裂が拡大したりします。
豪雨・台風→排水の処理能力を超える大量の雨水が浸透することで、土圧が急増し、亀裂部分から土砂が流出したり、擁壁自体が外側に押されたりします。
経年劣化と自然災害は、安全性を大きく左右する要因です。特に古い擁壁を所有している場合は、これらのリスクを踏まえ、定期的な専門家による診断を検討することが賢明な判断と言えます。
実は深刻!「施工の不備・欠陥」と「地盤の弱さ」による構造的な問題
擁壁の不具合は、完成したときには見えない施工の不備・欠陥や地盤の弱さといった構造的な問題に起因することも多く、経年劣化や自然災害が加わることで、致命的なトラブルに発展します。特に、古い擁壁や建設時の記録がない場合は注意が必要です。
擁壁は、設計通りに必要な鉄筋が配置され、適切な強度を持つコンクリートで施工されることが絶対条件です。しかし、施工時に鉄筋が不足していたり、擁壁の基礎となる地盤調査や改良が不十分だったりすると、擁壁が持つべき強度や安定性が確保されず、早い段階で構造的な欠陥があらわになります。
擁壁は地中に埋まっている部分が多く、完成後にこれらの構造的な不備を見つけるのは困難です。特に古い擁壁や、造成された経緯が不明な土地を購入する際は、地盤の問題や不適格擁壁の使用がないかを専門家による調査で確認することが、最も重要なリスク回避策となります。
擁壁のトラブルは様々な要因から発生することを解説してきました。特に、排水の不良は擁壁崩壊の最も直接的で最大の要因であり、不適格擁壁や施工の欠陥は、耐久性そのものを損なう構造的な問題です。擁壁を守るためには、これらの原因を単体で考えるのではなく、複数のリスクが重なり合うことで事故につながるという危機意識を持つことが重要です。
事故を未然に防ぐ!擁壁の定期的な点検項目

問題が深刻化する前に自分の擁壁を守るために何をすべきかという具体的な対策が重要になります。擁壁は、所有者による日々の注意深い管理と定期的な専門家の診断によって、安全性を維持できます。ここでは、個人でもできるセルフチェックの具体的な項目と、専門家に相談すべきサインについて解説します。
今日からできる!擁壁のセルフチェック「5つの点検項目」
擁壁の重大な事故を未然に防ぐためには、所有者自身が5つの点検項目を定期的にチェックし、異常のサインを早期に発見することが非常に重要です。日常の目視点検は、擁壁の異変を知らせる最も早くて最も安いチェックの仕方です。👀
擁壁の不具合は、突発的に起こるのではなく、ひび割れや漏水といった目に見える小さな予兆から進行するケースがほとんどです。日々のセルフチェックを行うことで、専門家を呼ぶべきタイミングを適切に見極め、事故リスクと修理費用を最小限に抑えることができます。
セルフチェックで確認すべき「5つの点検項目」と異常のサインは以下の通りです。
・亀裂(ひび割れ)の有無:擁壁に水平または垂直の長いひび割れがないか確認します。
異常のサイン:亀裂の幅が0.2mm以上ある場合、または亀裂から水が流れ出ている場合は構造的な問題の可能性があります。
・水抜き穴の機能:水抜き穴が泥や草、ゴミなどで詰まっていないか確認します。
異常のサイン:穴から水が全く出ていない、あるいは普段とは違う場所から水が染み出している場合は、背面に水が溜まっている証拠です。
・変形(傾き・はらみ):擁壁が外側(道路側)に膨らんでいないか、または片側だけに傾いていないかを定規や目視で確認します。
異常のサイン:擁壁の天端(一番上の面)が水平でない場合や、壁面に明らかな曲線状の膨らみが見られる場合は、土圧に耐えきれなくなっている危険信号です。
・擁壁上部と周辺の状況:擁壁の上の地盤に大きな樹木が接近していないか、また水たまりができていないか確認します。
異常のサイン:近くの木の根が擁壁に食い込んでいる、または上部で雨水が溜まって擁壁の裏側に浸透しやすい状態になっている場合は、劣化を促進します。
・コンクリートの劣化(爆裂・剥離):コンクリートの表面が剥がれていないか、また内部の鉄筋が露出して錆びていないか確認します。
異常のサイン:鉄筋の錆びによるコンクリートの欠けが見られる場合は、強度が著しく低下している状態です。
セルフチェックは年に数回、特に大雨や地震の後に行うことが大切です。上記5つの項目のいずれかに異常なサインが見られた場合は、自己判断せず、すぐに専門業者に相談し詳細な診断を依頼しましょう。
専門家に相談すべきサインと「補修・修理」の選択肢
セルフチェックでリスクを示すサインを発見した場合、自己判断で終わらせずにすぐに専門の業者に診断を依頼することが、事故を防ぐための正しい行動です。専門家の診断に基づき、擁壁の状態に応じた適切な補修・修理方法を選びましょう。
擁壁の内部で起きている問題は、素人の目視だけでは正確に把握できず、放置すれば急激に崩壊リスクを高めます。また、専門家は現在の擁壁が現行の建築基準に適合しているかを判断できるためリスクに応じた最適な補修方法(部分的な修理か全面的なやり直しかなど)を提案できます。
専門家に相談すべきサインは以下の通りです。
・ひび割れが拡大している(前回より幅が広がっている、または長く伸びている)。
・擁壁に明らかな傾きや膨らみが見られる。
・鉄筋が露出し、コンクリートが剥がれている(爆裂)箇所がある。
・水抜き穴ではない場所から常に水が染み出している。
擁壁の主な補修・修理の選択肢は以下の通りです。
・部分補修(軽度の異常):ひび割れに樹脂を注入したり、水抜き穴の清掃や再設置を行ったりする、比較的軽い対応です。
・構造補強(中度の異常):傾斜地の土を掘削せずに、擁壁を支えるための杭を打ち込んだり、モルタル吹き付けやアンカー(地中固定具)で構造を強化する工事です。
・全面改修(重度の異常):不適格擁壁の撤去や、ひどく老朽化した擁壁を解体し、L型擁壁などの現行基準に適合する新しい擁壁に造り直す工事です。
専門家に相談する際は、擁壁診断士や地盤調査会社などの擁壁や地盤に特化した実績を持つ業者を選びましょう。早期の診断は、大事故のリスクを回避するだけでなく、修理費用を最小限に抑えることにもつながります。
まとめ
擁壁は、土砂崩壊を防ぐ「命の壁」ですが、劣化を放置すると、大事故と高額な賠償責任という最悪の事態につながることもあります。特に、水抜き穴の機能不全や古い擁壁(不適格擁壁)の放置は、擁壁崩壊の二大要因です。
擁壁トラブルを避けるため今日からできる行動として目視点検があります。ぜひ一度チェックしておいてください。命と大切な資産を守りましょう!🏠
素敵なふつう
イチマルホームは岡山県内全域での施工実績があります。些細なことでも、気になる点がございましたら、お近くの店舗(赤磐店・岡山店・総社店・倉敷店がございます)にお電話やメール、SNSでのご連絡等で、お気軽にご相談ください!いっしょに考える総合的なお手伝いをさせていただきます。
2025.10.30
✍️関連ブログのご紹介
地盤のお話→住宅購入は地盤の安心から
土地選びのお話→土地選び
このブログ記事もおすすめ!






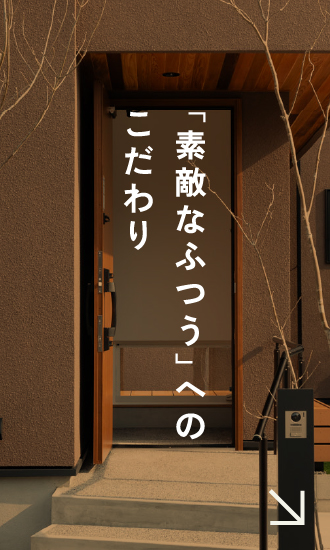



 家づくり相談
家づくり相談 来場予約
来場予約 カタログ請求
カタログ請求