
ブログ
住まいの豆知識から
暮らしのヒントなどご紹介
このブログ記事もおすすめ!
インテリアカラーの決め方|おしゃれに見せる配色テクニック

こんにちは!広報の中村です💁♀️
今回は、インテリアの配色についてご紹介します。
おしゃれな部屋づくりのポイントとして、インテリアの色を上手に組み合わせるだけで印象や居心地の良さは大きく変わります。
この記事では、インテリアカラーの基本ルールから、失敗しない配色のコツ、そしておしゃれに見せるテクニックまでわかりやすく解説します😊
おしゃれなお部屋づくりに興味がある方は、ぜひ読み進めてみてください!
目次
ベースカラー・アソートカラー・アクセントカラーの3色バランス(70:25:5の法則)
インテリアカラーで部屋の印象は変わる

部屋の印象を左右する要素のひとつが「色」です。
同じ間取りでも、壁や床、家具の色を変えるだけで、空間の広がり方や雰囲気、居心地までもが大きく変わります。たとえば、淡いベージュは温かみを、グレーは洗練された印象を、グリーンは安らぎを感じさせます。
色には人の感情に働きかける「心理効果」があり、また明度や彩度の違いによって、空間の広さや明るさの見え方も異なります。
ここでは、色がもたらす心理的な影響や、明度・彩度が与える視覚効果、そして実際の事例を通して“同じ間取りでも印象がどれほど変わるか”を見ていきましょう。
色がもたらす心理効果
「色彩心理学」という学問をご存じでしょうか?これは色が人の感情や行動に与える影響を研究する学問のことです。学問として研究されているように、色には影響力があるのです。
例えば、「膨張色」も色が与える影響によるものです。膨張色が同じサイズでも大きく見える色であるのに対して、小さく見える収縮色というものもあります。その他には、「進出色と後退色」「興奮色と鎮静色」などがあります。
また、勉強するときに青色がいいと言われるのは、青色が勉強中のストレスを軽減し、集中力を長く持続できるという効果があるためです。(もちろん個人差はあります)
このように、色は見た目の印象だけでなく、気分や行動にも影響を与える大切な要素です。インテリアに上手に取り入れることで、「落ち着く空間」や「活気のある空間」など、理想の雰囲気を演出することができます。まずは自分や家族がどんな気分で過ごしたいのかを考えて、カラーを選ぶことが心地よい住まいづくりの第一歩です。
明度・彩度が空間に与える影響
部屋の印象を大きく変えるポイントのひとつが、「明度」と「彩度」です。
同じ色でも、明るさや鮮やかさの違いによって空間の見え方がまったく変わります。
明度とは色の明るさのことで、明度が高いほど軽やかで広がりを感じる空間になります。
一方で、明度が低い色を使うと落ち着きや高級感を演出できます。
彩度とは色の鮮やかさのことで、彩度が高い色は元気で活発な印象を与え、彩度が低い色はやわらかく上品な雰囲気をつくります。
例えば、リビングの壁を明度の高いベージュにすると、自然光が反射して空間が広く見えます。子ども部屋に明るいイエローやミントグリーンなど、彩度の高い色を取り入れると、楽しくエネルギッシュな印象になります。
反対に、寝室を深いグレーなど、明度と彩度を抑えた色でまとめると、落ち着いた雰囲気になります。
このように、明度と彩度のバランスを意識して配色を考えることで、同じ間取りでも空間の印象を自由にコントロールすることができます。
同じ間取りでも「色」でここまで変わる
ここまで、色が持つ心理効果や明度・彩度についてご紹介してきました。実際に施工実例の写真(before)の一部を変えて色による印象の違いの例を3つ見ていただこうと思います!
①明度を高く
和室の吊戸棚の襖の色を変えてみました。
before:落ち着いたピンク → after:明るいピンク


②彩度を低く
ドアの色を変えてみました。
before:淡い水色 → after:薄いグレー


③補色に変更・彩度を高く
クッションの色を変えてみました。
before:落ち着いた緑色 → after:彩度を高くした赤色


部屋の一部の色が変わるだけで、受ける印象は大きく変わったのではないでしょうか。
このように、インテリアの色が与える影響は大きいです!
おしゃれに見せるインテリアカラーの基本ルール

センスの良い部屋に見せるためには、感覚だけで色を選ぶのではなく、配色の「基本ルール」を押さえておくことが大切です。
ファッションと同じように、ベースとなる色・引き立てる色・アクセントとなる色のバランスを意識するだけで、まとまりのある洗練された空間に仕上げることができます。
ここでは、初心者でも取り入れやすい配色の考え方と、色選びで失敗しないためのポイントを解説します。
ベースカラー・アソートカラー・アクセントカラーの3色バランス(70:25:5の法則)
部屋をおしゃれに見せるには「70:25:5」のバランスを意識するのがポイントです。
この法則は、部屋全体の色をベースカラーを70%、アソートカラーを25%、アクセントカラーを5%の3つに分けて考える方法です。色の割合を考えることで、空間にまとまりが生まれ、洗練された印象を簡単につくることができます。
例えば、壁や床、天井などの広い面積を占める部分はベースカラーで、ベージュやホワイトなどの明るい色を使います。家具やカーテンなど、中くらいの面積のアイテムはアソートカラーでまとめ、グレーやブラウンなどを選び、全体に深みを出します。最後に、クッションやアート、照明や雑貨などの小物でアクセントカラーを取り入れると空間が引き締まり、おしゃれな印象になります。
色をたくさん使うよりも、割合を意識してバランスよく使うのがセンスの良さにつながります。まずは、この法則を意識することから始めてみましょう。
暖色・寒色・中間色の特徴を知る
部屋の印象を大きく左右するのが、色の温度感です。暖色・寒色・中間色の特徴を理解しておくことで、空間の雰囲気を思い通りに演出できます。
以前、【照明で魅せるおしゃれ空間のつくり方|注文住宅で失敗しない照明計画】のブログでも色温度についてご紹介しましたが、今回も似ています。同じ間取り・同じ家具でも、使う色の系統が違うだけで空間の感じ方は大きく変わります。
暖色はぬくもりや親しみを与えるのに対し、寒色は清潔感やクールな印象を感じさせます。中間色はそのどちらにも偏らず、ナチュラルで落ち着いた印象をつくりやすいのが特徴です。
例えば、リビングにオレンジやベージュなどの暖色を取り入れると、家族が自然と集まるあたたかみのある空間になります。
一方、寝室や書斎にブルーやグレーなどの寒色を使うと、心が落ち着き集中しやすい環境になります。
グレージュやオリーブのような中間色は、ナチュラルインテリアや北欧テイストとの相性がよく、飽きのこない上品な印象に仕上がります。
色の系統を意識することで、空間に”温度”を与えることができます。どんな気持ちで過ごしたい部屋なのかを考えながら、暖色・寒色・中間色を上手に使い分けることも快適な生活のためには重要です。
素材や照明によって変わる色の見え方
同じ色でも、そのものの素材や同じ部屋に置く照明の種類によって見え方は変わります。インテリアカラーを選ぶときは、色そのものだけでなく、どんな素材でどんな光の中で見るかも意識する必要があります。
光は反射の仕方によって色の印象を変えます。ツヤのある素材は光を強く反射して明るく見え、マットな素材は落ち着いたトーンに見えます。また、照明の色温度によっても、壁紙や家具の色味が変化して見えることがあります。
たとえば、同じ白い壁紙でも、昼間の自然光ではすっきりとした明るい白に見え、夜に電球色の照明を当てるとやや黄みがかった温かい印象になります。
また、木材のような自然素材は光を柔らかく吸収するため、落ち着いた雰囲気に感じられるのに対して、金属やガラス素材は光を反射するためクールでスタイリッシュな印象をつくります。
色で決める前に、素材や光の条件を踏まえて色を選ぶことで、理想の空間を再現しやすくなります。
失敗しないインテリアカラーの選び方

おしゃれな部屋づくりを目指しても、実際に色を選ぶ段階で迷ってしまうという人は多いものです。前述のような色選びの理論を知っていても、サンプルやカタログの小さな色だけで判断するのは意外と難しいです。
ここでは、色選びで後悔しないための具体的なポイントを3つに分けてご紹介します。実際の空間をイメージしながら進めることで、理想のインテリアカラーをより確実に形にできます。
色見本やカタログを自然光で確認する
色選びは、自然光の下でも色をチェックすることが大事です。これは、繰り返しになりますが、照明の種類や時間帯によって、同じ色でも違う色に見えることがあるためです。インテリアショップでは、それぞれに適した間接照明等を置いている場合もあります。そのため、できれば色見本やサンプルなどを窓際に行って自然光で確認できるのがベターです。もしくは、どのような照明と組み合わせるかまで先を見て検討するのがおすすめです。
床・建具など「固定要素」から決める
インテリアカラーは、まず動かせない固定要素(床や建具、造作家具や窓枠など)から決めるのが基本です。これらは後から簡単に変えられないため、最初に決めて基準にすることで統一感がある部屋に仕上げることが簡単になります。
部屋全体のトーンを統一する
おしゃれな空間をつくるためには、部屋全体のトーン(明度と彩度の組み合わせによって決まる色の調子や印象)を統一することが大切です。
同じ色味でも、明るさや彩度の違いによって印象がバラバラになってしまうからです。
例えば、床は明るいナチュラルカラー、家具は濃いブラウン、カーテンはビビッドカラーなど、トーンが揃っていないとまとまりのない印象になります。
まとまりを持たせるために、全体をペールやライトグレイッシュなどの淡いトーンでまとめれば、ナチュラルで柔らかい雰囲気になり、ディープやダークなど暗くて濃いトーンで統一すれば重厚感のあるモダンな印象になります。
トーンを決めるときは、まず「どんな雰囲気の部屋にしたいか」を考え、そのイメージに合わせて色の明るさや鮮やかさを揃えるのがポイントです。トーンを統一することで、色数が多くてもスッキリと見え、空間に一体感が生まれます。インテリアカラーの仕上がりをグッとおしゃれに見せる、シンプルながら効果的なコツです。
おしゃれに見える配色テクニック

ここからはおしゃれに見せるためのひと工夫をご紹介します。同じ色でも組み合わせ方や見せ方次第で、空間の印象はがらりと変わります。
トーンを揃えて落ち着いた雰囲気を出したり、異素材をミックスして立体感を生んだり、ちょっとした工夫でセンスよく見える配色がつくれます。
アクセントクロスや小物で「色の注目ポイント」をつくる
部屋の印象をグッとおしゃれに見せたいなら、アクセントクロスや小物で「色の注目ポイント」をつくるのがおすすめです。
どういうことかと言うと、全体をベースカラーでまとめた空間に、部分的に強めの色を入れることで視線を誘導するポイントを配置するということです。これは、空間にメリハリや立体感を生む効果があります。
例えば、リビングの一面だけを深いブルーのクロスにすると、壁全体がアクセントとなって家具やアートが映えます。また、クッションやラグなどの小物で赤やイエローなどのアクセントカラーを入れると、空間に遊び心とリズム感が加わります。さらに、照明の色味やフレーム素材と合わせると、統一感を損なわずに色のポイントを際立たせることができます。
つまり、アクセントクロスや小物を取り入れるだけで、簡単におしゃれで奥行きのある空間がつくれるのです。色の差し込み方を意識して、遊び心あるインテリアを楽しむことができます。
異素材ミックスで立体感をプラス
少し色の話からは逸れてしまいますが、おしゃれな空間をつくるには、異なる素材を組み合わせることもひとつの手です。
色味を揃えて統一感を出した上で、素材に変化をつけることで立体感が生まれます。
例えば、木目×アイアン×ファブリックのように、自然素材と無機質な素材をバランスよく組み合わせると、単調にならず洗練された印象になります。
同じベージュトーンでも、リネンのソファ・ウッドの家具・ラグの毛並みといった質感の違いで奥行きが感じられます。
逆に、すべてツルツルした素材でまとめると平面的に見え、のっぺりとした印象になってしまうこともあるので、注意が必要です。
このように、異素材を上手にミックスすることで、同系色の空間でも深みのあるおしゃれなインテリアに仕上がります。
まとめ
インテリアの色は気持ちや居心地、空間の印象に大きな影響を与えます。明度・彩度・トーンを意識して配色を整えるだけで、同じ間取りでも居心地がよくなったり、洗練された印象になったりします。
今回特に意識したいポイントは以下の4つです。
・70:25:5の法則
・色見本やカタログを自然光で確認する
・床・建具など「固定要素」から決める
・部屋全体のトーンを統一する
これらを踏まえた上で、素敵なお部屋づくりを楽しんでいただけたらと思います😊
素敵なふつう
今回使用した画像は、イチマルホームが実際に担当させていただいた住宅です。
「どんなインテリアにしたらいいかわからない」「どんな配色にしたらいいのかわからない」など、どんなお悩みもぜひご相談ください😊
イチマルホームは岡山県内全域での施工実績があります。些細なことでも、気になる点がございましたら、お近くの店舗(赤磐店・岡山店・総社店・倉敷店がございます)にお電話やメール、SNSでのご連絡等で、お気軽にご相談ください!いっしょに考える総合的なお手伝いをさせていただきます。
2025.10.23
✍️関連ブログのご紹介
色にフォーカスした施工事例のお話→【事例紹介】Vol.4<前編>クールなご夫婦に似合う、シックで個性的な内外装
トイレのインテリアのお話→おしゃれなくつろぎ空間を演出するために トイレのインテリアにこだわろう!
~2025.11.11追記~
Instagramに【特集】心地よい配色術を投稿しました!ご覧ください^^
このブログ記事もおすすめ!






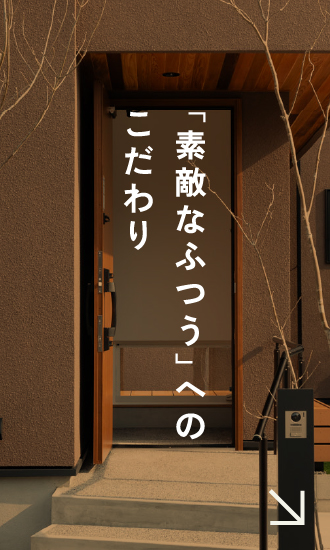



 家づくり相談
家づくり相談 来場予約
来場予約 カタログ請求
カタログ請求