
ブログ
住まいの豆知識から
暮らしのヒントなどご紹介
このブログ記事もおすすめ!
注文住宅に和室は必要?メリット・デメリットと後悔しない選び方

こんにちは🌞広報の中村です!
注文住宅を建てるときに「和室は必要?」と悩む方は多いものです。
昔ながらのイメージがある一方で、畳の快適さや多目的に使える便利さから、現代の住まいでも根強い人気があります。ただし、注意すべきデメリットもあります。
今回は和室のメリットやデメリットに加え、失敗しないための和室づくりのアイデアをご紹介します。
お家に和室が必要かどうか悩んでいる方に読んでいただきたいです!参考になれば幸いです💁♀️
目次
和室の魅力とは?和室のメリット

和室には、洋室にはない独特の魅力があります。畳のある空間は心を落ち着かせ、来客時や子育て、リラックスタイムなど、さまざまな場面で活躍します。ここでは、現代の暮らしに取り入れることで得られる和室のメリットをご紹介します。
多目的に使える空間になる
和室は一部屋で多様な使い方ができる、柔軟性の高い空間です。
畳の上は座布団や布団を敷けば寝室になり、テーブルを置けば客間や団らんの場に早変わりします。床に直接座る文化に合わせてつくられているため、家具を多く置かなくても快適に過ごせるのが特徴です。
たとえば、小さなお子さんのお昼寝スペースとして利用したり、親戚や友人が泊まりに来た際にはそのまま客間にしたりと、ライフスタイルに合わせて活用できます。また、リビング横に設ければ、家族の気配を感じながら読書や仕事をする「セカンドリビング」としても便利です。
このように和室は、多目的に使うことができる柔軟さが魅力で、家族の成長や暮らしの変化に長く対応してくれる空間と言えます。
畳ならではの快適さがある
畳にはフローリングにはない柔らかさと温かみがあり、心地よい暮らしを支えてくれます。
天然のい草を使った畳は適度なクッション性があるため、歩いても座っても疲れにくいです。転倒したときもケガをしにくいというメリットもあります。また、冬はひんやりしにくく、夏はさらっと涼しい肌触りになるのも特徴で、素足でも気持ちよく過ごすことができます。畳のやわらかさは安心感を与え、お昼寝やストレッチ、読書などちょっとしたリラックスタイムにもぴったりです。
和室ならではの心地よさを一年を通じて日常に取り入れることができます。
畳には調湿効果がある
畳には自然素材ならではの調湿効果があり、快適な室内環境を保つことができます。
い草の内部はスポンジのような構造をしており、湿気が多いときには水分を吸収し、乾燥しているときには水分を放出します。そのため、梅雨のジメジメや冬の乾燥をやわらげ、室内の湿度をほどよく整えてくれるのです。
たとえば梅雨の時期でも畳の部屋はカラッと感じやすく、逆に冬は乾燥によるのどの痛みや肌の乾燥をやわらげる効果が期待できます。エアコンや加湿器などの家電製品に頼りすぎずに快適さを維持できるのも魅力です。
自然に心地よい室内を保ってくれるエコな素材です。
和室は畳の心地よさや調湿効果だけでなく、多目的に使える柔軟な空間としても魅力的です。リラックスできる空間や来客時の応接、子どもの遊び場など、ライフスタイルに合わせて活用できるのが大きなメリットです。和室の特性を理解して取り入れることで、快適で落ち着きのある住まいづくりにつながります。
後悔しないために知っておくべき和室のデメリット

和室には汎用性や快適さなど多くの魅力がありますが、実際に暮らしてみると「思っていたより大変だった」と感じる場面も少なくありません。畳の手入れや家具の配置など、和室ならではの注意点を理解しておかないと後悔につながってしまうことも。
ここでは、和室をつくる前に知っておきたいデメリットをまとめました。
畳のメンテナンスが必要
畳は快適さがありますが、この快適さを保つためには定期的なメンテナンスが欠かせません。自然素材のため、湿気や汚れ、日焼けの影響を受けやすく、放置すると劣化や変色が進んでしまいます。
メンテナンスは数年ごとに、畳の裏返し・表替え・新調が必要で、日常的には掃除機や換気をして湿気や汚れを防ぐことが求められます。
快適さを保つには、少し手間がかかることを理解しておくことが大切です。
重たい家具を置きにくい
畳は重たい家具を置くと傷みやすいため、設置には注意が必要です。
やわらかい素材なので、家具の重さでへこみや傷ができやすく、長期間同じ場所に置くと畳が変形してしまいます。
たとえば、ソファや大型の収納棚を畳の上に直接置くと、重さがかかった部分に跡が残ってしまいます。
家具を置く場合は脚と畳の間にフェルトなどの保護材を使ったり、こまめに位置を変えるなどの工夫が必要です。
ダニやカビが発生しやすい
和室の畳は、普段のお手入れをサボるとダニやカビが発生しやすい点に注意が必要です。
調湿効果があるため、湿気を吸収しやすく、通気性が悪い環境ではダニやカビが繁殖しやすくなってしまいます。
たとえば、梅雨の時期に布団を敷きっぱなしにすると、湿度が高く吸収するのに換気することができず通気性は最悪です。このような場合、温床になってしまいます。
これを防ぐためには、定期的な換気や乾拭きなどで湿度を下げることが重要です。
和室には畳のメンテナンスや家具の配置、湿気対策など注意すべき点もあります。これらのデメリットを理解しておくことで、実際に暮らしてからの後悔を防ぐことができます。和室を取り入れる際は、ポイントを踏まえて計画することが大切です。
和室づくりに失敗しないためのアイデア

和室は魅力的な空間ですが、こだわりなく和室をつくると使い勝手や見た目で後悔してしまうこともあります。ここでは、和室を快適で機能的にするためのポイントや工夫のアイデアをご紹介します。
デザインにこだわる
和室をつくるときは、デザインにこだわることで空間の雰囲気がぐっと引き立ち、お気に入りの場所になります。
畳や床の色、壁紙、照明、建具のデザインによって、和室全体の印象は大きく変わります。デザインに統一感があると、居心地がよい落ち着く空間になります。
たとえば、ナチュラルテイストのリビングに合わせて明るめの畳と木目の建具を選ぶと、リビングとの一体感が生まれます。逆に、モダンな空間に濃い色の畳やシンプルな壁紙を合わせると、落ち着きながらもスタイリッシュな印象になります。
デザインにこだわることで、和室がただの寝室や来客用の部屋ではなく、家全体の雰囲気に合ったり、アクセントを加えたりと、魅力的な空間になります。
収納スペースを確保する
和室には収納スペースを取り入れることで、より使い勝手の良い空間になります。
布団や座布団など、和室ならではのアイテムはかさばるためそれらをきちんと片付けられるスペースは大切です。
たとえば、吊り押入れやニッチ、和室の奥にヌックを設置したり、小上がりの和室であれば引き出しの収納をつけたりと、収納スペースのアイデアはたくさんあります。
さらに、収納の扉や仕上げを畳や壁材と調和させることで、見た目にもすっきりとした和の雰囲気を保つことができます。限られたスペースでも工夫次第で収納力を高められるため、家族のライフスタイルに合わせて設計することがポイントです。
仕切りをつけて2wayに
和室に仕切りを設けると、空間を用途に応じてより柔軟に使い分けられるようになります。ひとつの部屋をつなげたり、区切ったりできるため、暮らしのシーンに合わせたアレンジがしやすいのが大きな魅力です。
たとえば、引き戸や障子、スクリーンなどで仕切れば、来客時には独立した客間として活用でき、普段は仕切りを開けてリビングと一体化させることで広々とした空間に変えられます。また、小さなお子さまがいる家庭では、普段は仕切りを開けて家族の目が届く遊び場として使い、集中したいときには閉めて静かな勉強スペースにするなども可能です。
さらに、最近では在宅ワークの増加により、和室をワークスペースとして使うケースも増えています。仕切りを閉めるだけで簡易的な書斎になり、仕事と生活のオンオフを切り替えやすくなるのもメリットです。
仕切りを工夫することで、限られた空間を無駄なく使える「2way仕様の和室」が実現します。デザイン性や素材、開閉のしやすさなどを考慮して選べば、日常の暮らしにフィットする使い勝手の良い和室になります。
和室を取り入れる際は、デザイン性・収納・仕切りの工夫によって使い勝手と快適さが大きく変わります。伝統的な和の雰囲気を残しつつも現代的なライフスタイルに合う工夫を加えることで、より実用的で長く使用できる空間になります。家族構成や暮らし方に合わせたアイデアを取り入れれば、後悔のない和室づくりが叶います。
まとめ
注文住宅に和室を取り入れるかどうかは、多くの方が悩むポイントです。和室には多目的に使える、心地よさ、調湿効果などのメリットがある一方で、メンテナンス必須、重たい家具の制限、ダニやカビといったデメリットも存在します。
しかし、デザインや収納、仕切りの工夫を取り入れることで、デメリットをカバーしながら和室の魅力を最大限に活かすことができます。和室は暮らしにやすらぎを与え、現代的な住まいの中でも多彩な用途で活躍する空間です。ご家族のライフスタイルに合わせて計画してみてください。
素敵なふつう
今回使用した画像は、イチマルホームが実際に担当させていただいた住宅です。(※1枚フリー画像)
イチマルホームは岡山県内全域での施工実績があります。些細なことでも、気になる点がございましたら、お近くの店舗(赤磐店・岡山店・総社店・倉敷店がございます)にお電話やメール、SNSでのご連絡等で、お気軽にご相談ください!いっしょに考える総合的なお手伝いをさせていただきます。
2025.10.09
✍️関連ブログのご紹介
畳のお話→和の心をいつまでも大切に!畳の種類と特徴
このブログ記事もおすすめ!

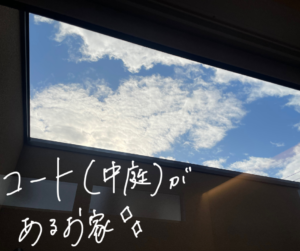




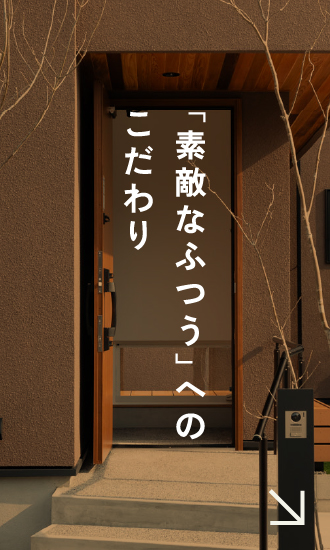



 家づくり相談
家づくり相談 来場予約
来場予約 カタログ請求
カタログ請求